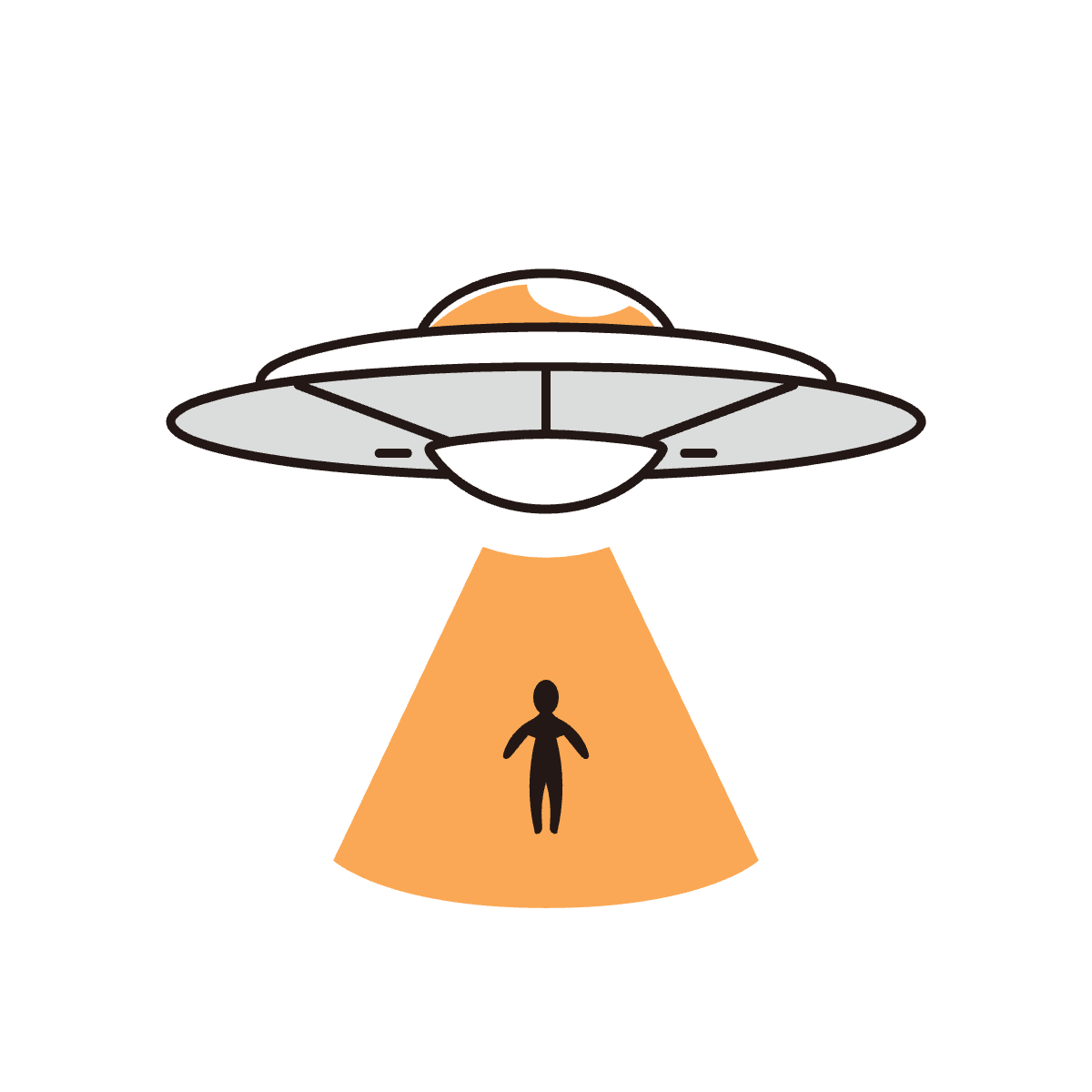

今回は壮大で夢のあるテーマ。
SF映画で見る、曲線が滑らかな建物とか、光をまとったような乗り物って、
なんで「未来だ」と直感的に感じるんでしょうね。
見たことがないはずなのに、
「いや、これは未来なら確かにあり得る」と思わせてくる。
僕はこの“説得力の正体”がずっと気になっていて、
いろんな作品を観たり、デザインを学んだりしてきた中で、
未来の形は、今の技術が“進化したらこうなる”という納得感の延長にある
ということが見えてきました。
無理に奇抜にしようとしたものより、
“合理性が進みきった結果の形”の方が、むしろ未来に見えるんです。
そのあたり、今日はじっくり一緒に考えていければ嬉しいです。
未来のかたちってどんなもの?(遠未来)
ここからは、僕がいろんなデザインに触れてきて思う
「未来らしい形の特徴」を、一つずつ深掘りしながら紹介します。
なんとなく眺めるだけでも面白いと思いますし、
デザインやアートをしている方なら、
自分の表現にそのまま応用できる部分もあると思います。
① 直線と曲線の“混ざり方”が今とは違う
未来の形って、丸いだけでも尖っているだけでもないんですよね。
-
大きくてなめらかな母体(丸み)
-
最小限の鋭さ(直線)
が共存しています。
このバランスがちょっと不思議で、
「自然のものなのか人工物なのか」判定できない感じがして、
そこに“未来感”が生まれるんだと思います。
生物の進化みたいに、有機的でありながら、
人工物の緊張感も感じる。
絶妙なんですよね。
② 外殻が“ひとつながりの皮膚”みたいになる
未来のプロダクトって、
まるで内側にパーツがあることを感じさせません。
-
境界がない
-
ひとつの連続したシェル
-
面が途切れずつながっている
この“つるんとした存在感”は、
現代では技術的に難しいけれど、未来ならできてそうなんですよね。
ロボットの外装とか、建物の壁とか、
未来作品はこの見せ方が本当に上手いです。
③ 素材が混ざっていく(境界が曖昧になる)
未来は、素材の区別が弱くなると考えています。
-
透明なのに硬い
-
金属なのに柔らかい
-
樹脂なのに光を通す
-
ガラスなのに割れない
みたいな、“ありえない質感”が自然に見える。
こういう素材って、それ単体で未来っぽいですよね。
現代の価値観だと衝撃ですけど、
未来なら普通に量産されてそうだな、という説得力があります。
④ 情報量が“とにかく少ない”のに美しい
未来のものって情報が少ないのに、逆に存在感が増すんですよ。
-
色数が少ない
-
線が少ない
-
模様がない
-
素材の主張が控えめ
つまり、
「ノイズのなさ」=「未来の静けさ」
なんですよね。
心理学的にも、
人は“情報が整理されたもの”に安心を覚えるので、
合理性と未来性は相性が良いのだと思います。
⑤ 光そのものが“素材”になる
現代では
「光=情報を伝えるための手段」
ですが、未来ではもっと根本的に変わっていて、
光が物の性質そのものになる
というイメージに近いです。
例えば…
-
呼吸するように光る
-
色が空気のようにゆっくり変化する
-
輪郭だけが淡く光る
-
情報の軌跡が空間に残る
-
光が形を持っている
こんな表現は、まだ僕たちの世界では無理だけど、
未来なら普通にあるかもしれませんよね。
“光との共存感”が未来を大きく感じさせます。
未来の形を実際に作りたいときの考え方
ここからは、実際のデザインにも使える部分です。
未来的に“見せるテクニック”ではなく、
未来の考え方から形を導き出す方法です。
① 現代の“不満”から逆算する
未来とは、
現代の欠点が改善された世界
なので、ここを起点にすると形が一気に未来へ向かいます。
-
壊れやすい → 境界が消える
-
操作が複雑 → ボタンが減る
-
落とす → 角がなくなる
-
パーツが多い → 一体化する
こうして“不満が消えた結果”として生まれる形は、
自然に未来へ寄っていきます。
② 一度、線を半分にしてみる
とてもシンプルですが効果抜群。
今ある形を、同じ意味で「線半分」で描けるか?
これを考えると、未来っぽさが一気に出ます。
整理される → ノイズが減る → 静けさが出る
未来はこの流れで説明できます。
③ 境界を曖昧にする
未来感の要です。
-
面と面を丸くつなぐ
-
段差を消す
-
色差を弱くする
-
素材の境界をぼかす
「今ではできなさそう」が、「未来にはできるかも」へ変わる瞬間です。
④ 光の扱いに“意味”をもたせる
未来は情報が少ない分、光の意味が強くなります。
-
状態の変化
-
生命的な呼吸
-
注意の喚起
-
存在そのものの演出
そして、ノイズが少ない世界だからこそ、
ひとつだけ光っている部分に“物語”が宿る
という効果があります。
光は未来表現の最強の武器です。
⑤ “気配のような色”を扱う
未来はカラフルではなく、気配のような形容しがたい色が似合います。
白 → 少し青
黒 → 少し茶
グレー → 少し緑
この「世界観の色」は、未来の静けさをつくる大事な要素です。
⑥ 常識の“裏側”を使う
現代の常識って、未来を考える上では宝物なんです。
-
ガラスは割れやすい → じゃあ割れないガラスなら?
-
金属はひらひらしない → 布みたいな金属は?
ここが崩れるだけで未来が出現します。
作品を作る時、わざと“常識を裏返す”という方法は本当におすすめです。
まとめ:未来の形は奇抜ではなく、必然の先にある
書いていて思いましたが、未来の形って
“奇抜”に見えることもあるのに、根っこはとても理性的です。
-
余計なものが少ない
-
素材が進化している
-
光が自然に存在している
-
情報と形が整理されている
-
静かで、なめらかで、曖昧
こうした積み重ねが、
「まだ存在しないけど、未来なら絶対ある」
という説得力を生み出します。
僕自身、未来的なデザインを考えるのは本当にワクワクするので、
これからもいろんな角度から探求していきたいです。
最後まで読んでくださってありがとうございました。
またお会いしましょう。
【参考】未来的デザインの専門用語
| 用語 | 意味 | 関連内容 |
|---|---|---|
| バイオミメティクス | 生物の構造・動きを模倣する技術 | 有機×人工のバランス |
| フルイドデザイン | 流体のような連続形状の思想 | 境界の曖昧さ、滑らかさ |
| オーガニックデザイン | 自然界の造形を取り入れたデザイン | 丸みのある母体の発想 |
| ニューモーフィズム | 柔らかな光と影で立体感をつくるUI手法 | 静けさと新しさの演出 |
| マテリアルデザイン | “素材”を前提にしたデジタル表現 | 情報と形の整理 |
| ミニマリズム | 不要な要素の徹底排除 | 未来の静けさ・合理性 |
いいねをいただけると、明日の活動の励みになります🙌
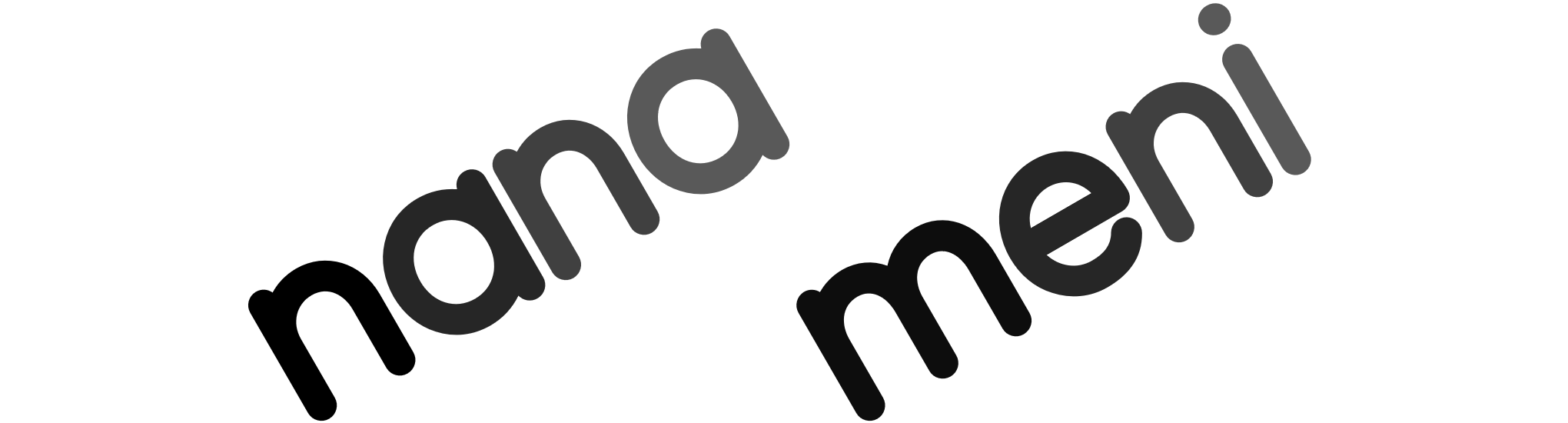

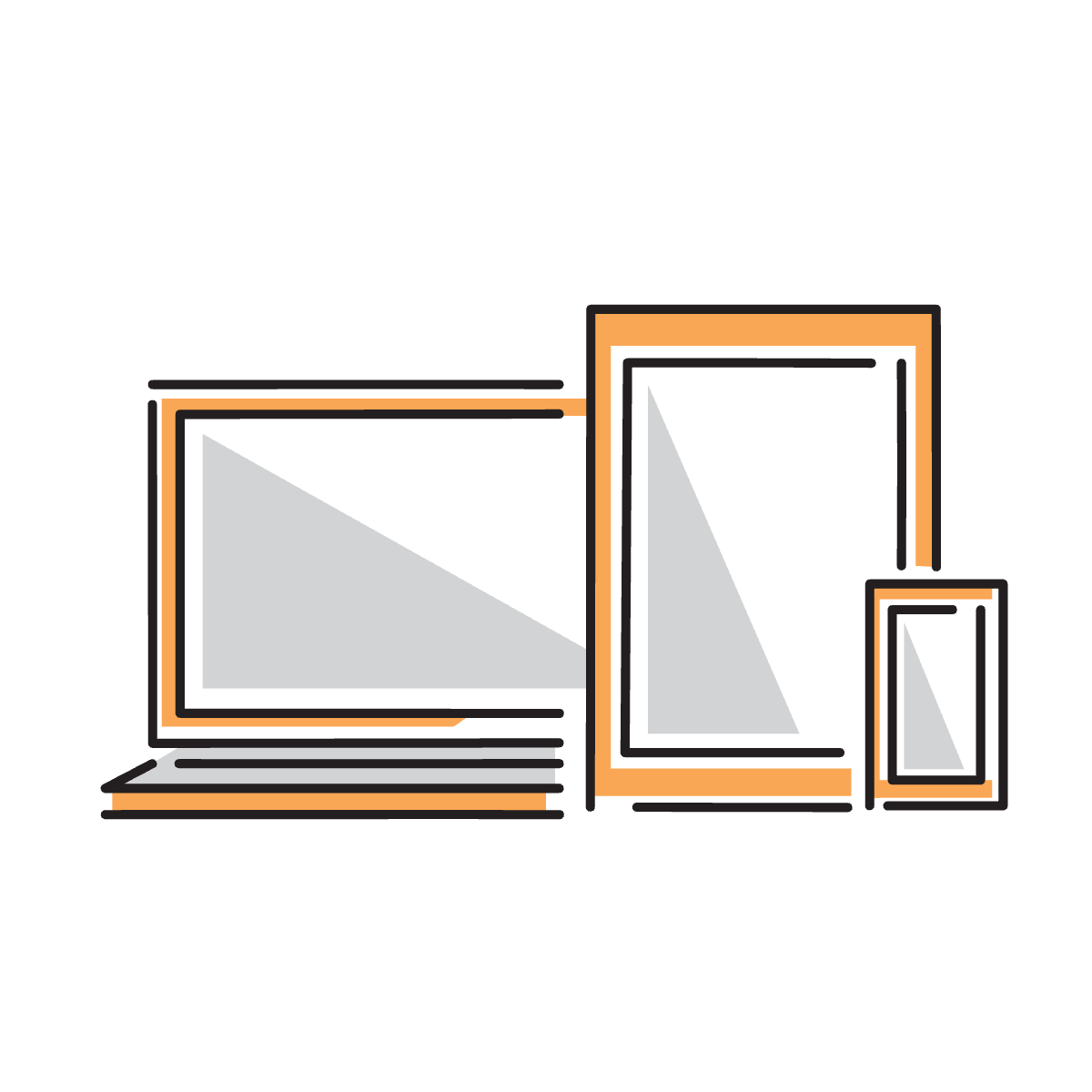
記事へのコメント