

最近、AppleがOSのUI全体に“透明感のある要素”を採用し始めたのをご存じですか?
iPhoneのコントロールセンター、ウィジェット、macOSのサイドバー…。
まるで磨りガラスを一枚かぶせたような、あの淡い透明感。
今ガラスのような透明感のあるUI(グラスモーフィズム)が注目されているのには、技術的な進化だけでなく、
“心理効果”や“デザイン哲学”の変化も大きいように思います。
今回は、透明感の魅力と、グラスモーフィズムの使いどころ、印象、実用性などを
例を交えながらじっくりまとめてみます。
今回も楽しんでいってください!
透明感とは何か
リアルな透明感は、「奥行き」×「柔らかさ」×「光の拡散」 が混ざった状態を指します。
透明=透ける
ではなくて、
“何かが透けながら、光によって美しく変化する状態”
なんですよね。
水・ガラス・霧・氷・光の膜。
これらすべて、“隠す”のではなく“透かして見せる”という特徴を持っています。
そして人は、この「透けて少しだけ見える」という曖昧さに
安心感や神秘性、奥行きを同時に感じるようです。
これは後で紹介する心理学とも深く結びついています。
グラスモーフィズムとは?
透明感をUIに取り入れた表現手法として有名なのが Glassmorphism(グラスモーフィズム)です。
特徴は以下の3つ。
-
背景が半透明でぼけて見える
-
淡い光(ハイライト)が縁に入る
-
ガラス板のようなレイヤー感がある
一言でいうと、
“UIの中に1枚の透明なガラスを置く手法”
です。
Appleはまさにこの「ガラス層」をOS全体に導入することで、
情報を階層ごとに整理しながら、世界観の統一感を作り上げているんです。
ちなみに厳密にはAppleのものはliquid Designというらしいです。
昨今「透明」が採用されている理由
これはただ流行っているからではなく、明確に効果があります。
① 情報の階層が自然に伝わる
透明=向こう側が見える
→ “これは背景より前にあるパネル” と判断できます。
つまり、透明なUIは“視覚的に優しい”ナビゲーションであるといえます。
② 印象が柔らかくなり、直感的に扱いやすい
色の主張が控えめで光も拡散されているので、
ナチュラルでユーザーが緊張しにくい利点があります。
③ 先進性や未来感を生む
透明 + 境界の曖昧さ = 未来の象徴。
都会ではガラスを多用したおしゃれな建物が多いですよね。
先進性や未来っぽさを出す最も簡単な方法のひとつが「透明感」だと言えると思います。
④ 新しいハードウェア性能にマッチしている
透明やぼかしは、昔は重くて選択しづらかった表現です。
それが、GPU性能が上がったこともあり、OS全体で自然に使えるようになりました。
“技術力の象徴” としての側面も大きいと思います。
透明感がもたらす心理効果
軽やかさ
透明は、重さを感じさせません。
同じ四角でも、
不透明 → 固い
透明 → 浮いている
という印象になります。
清潔さ・ピュアさ
水、ガラス=汚れのない世界
というイメージが自然と結びつきます。
美容・医療系のサイトで透明感が強いのはこれが理由でもあります。
高級感
ガラス、氷、光、煌めき → 高級な素材の象徴
これはジュエリー、ハイブランドでもよく使われる手法です。
解放感
すぐ目の前に真っ白・不透明の板がある状態と、透明なガラスがある状態を想像してみてください。
ガラスは向こうを見通すことができるので、圧迫感をあまり感じないと思います。
水族館で魚を見るときのように、目の前に何もない時とあまり変わらないほど自然に受け入れられるんです。
安心感
透明なものは背景を覆い隠すことがありません。
「視界の中に死角がない」という状態は、頭で考える以上に安心感に繋がります。
どんなときに使うと効果的?
① 階層を分けたいとき
ページを区切るのではなく、
“背景と少し距離をとる” ための手段として最適です。
-
サイドバー
-
パネル
-
モーダル
-
コントロールセンター
情報整理と相性抜群です。
② ミニマルデザインと組み合わせたいとき
透明なもので要素を置き換えれば、少ない色数で実現することができる場合があります。
線なども減らせるでしょう。
ノイズが少なくなり、視覚的にすっきりします。
③ 先進性・未来感を出したいとき
光との相性が非常にいいので、
先進性を出したり、近未来的なデザインを作るなら有力な候補です。
④ 写真や背景を活かしたいとき
繰り返しになりますが、透明は背景を隠さないということで、
写真などのメディアをベースにしたサイトでも邪魔をしません。
注意点
万能に見える透明感ですが、使いどころを間違えると逆効果にもなります。
文字が読みづらくなる場合がある
光を感じる明るい要素になりますので、
文字を載せる場合、色味に注意しないと視認性が下がってしまう場合があります。
写真などの背景の上にグラスUI、その上に文字をのせる、という場合も読みやすさを気をつけましょう。
コントラストについては別でまとめたいと思いますが、一般的には、
文字と背景とのコントラスト比は4.5:1以上というのが一つの基準です。
世界観を壊さずコントラスト比を確保できるよう調整しましょう。
グラスUIだけが浮く
これが意外と強敵なんですよね。
サイト全体の世界観が一致していないと“異物”になってしまいます。
「グラスUIを使うこと」そのものが目的になってしまうと、
全体としてみたときに、雰囲気と合っていないなんてことが起こりえます。
逆に古く見える場合がある
自然の見え方に近いような質感のグラスUIであればいいのですが、再現性が低い場合かえって古っぽい印象になることがあります。
例えば、PowerPointで文字にアクの強いグラデーションを多用したときのような。
これを防ぐためには、現実のガラスや優れたグラスUIを参考に、
光の反射や、透明感、淵のハイライトや影などを適切に設定する必要があると思います。
実用性はどうなのか
結論としては、
実用性と美しさのバランスがよく非常に優秀だと思います。
-
情報の階層化がしやすい
-
圧迫感がない
-
統一しやすい
-
UIとして自然
一方で、
-
コントラスト調整が難しい
-
全体の世界観作りが難しい
という注意点もあります。
まとめ
透明感・グラスモーフィズムは、一過性のある流行のようでいて、
実際はとても合理的で、人の心理にもマッチしたデザイン手法です。
-
柔らかさを感じる
-
先進的、未来的
-
軽さを感じる
-
安心感
-
高級感
-
情報の整理がしやすい
透明は“見せない”ではなく“見せながら整える”ための魔法。
皆さんもグラフィックやUIデザインを考える時にぜひ活用を検討してみてはいかがでしょうか。
今回も最後まで読んでいただきありがとうございました。
またお会いしましょう!
【参考】透明・UIに関する専門用語まとめ
| 用語 | 意味 | 関連内容 |
|---|---|---|
| グラスモーフィズム | ガラス風の半透明・ぼかしを用いたUI | Apple UI、未来感 |
| ブラー効果(Gaussian Blur) | 背景をぼかす効果 | 情報階層化 |
| トランスルーセント(半透明) | 透けるが輪郭が曖昧な状態 | 柔らかい印象 |
| ニューモーフィズム | 光と影で柔らかい立体をつくるUI | 透明との相性が良い |
| レイヤリング | UIを層として扱う設計思想 | OSデザイン全般 |
| ミニマリズム | 要素を減らして本質を残す思想 | 情報整理・透明感 |
| 視線誘導(Visual Hierarchy) | 人がどこを見るかを誘導する設計 | 階層化に透明を使う理由 |
いいねをいただけると、明日の活動の励みになります🙌
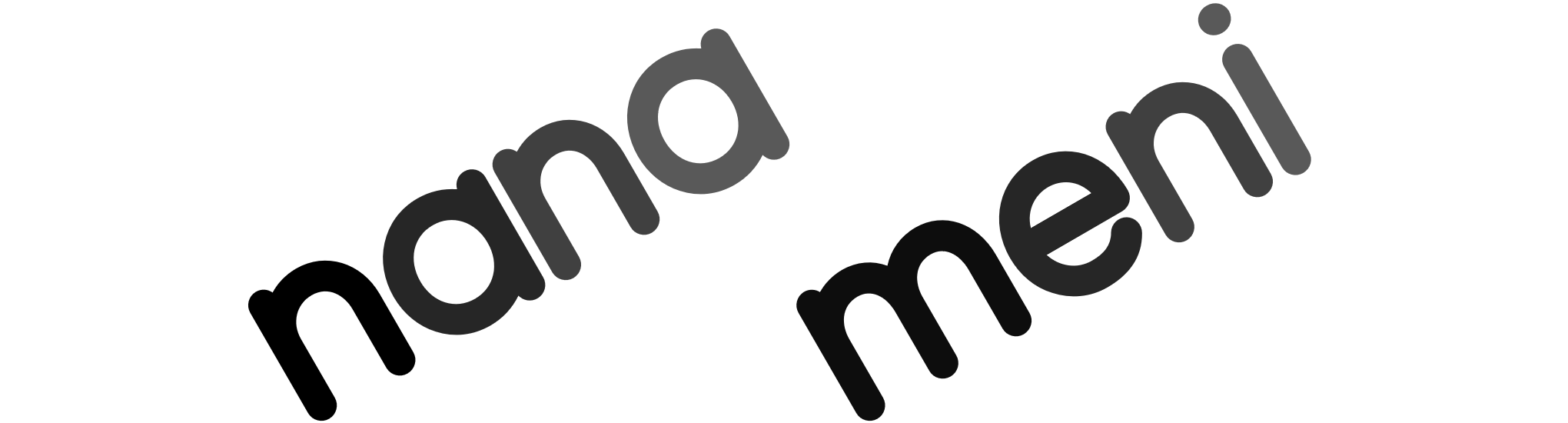


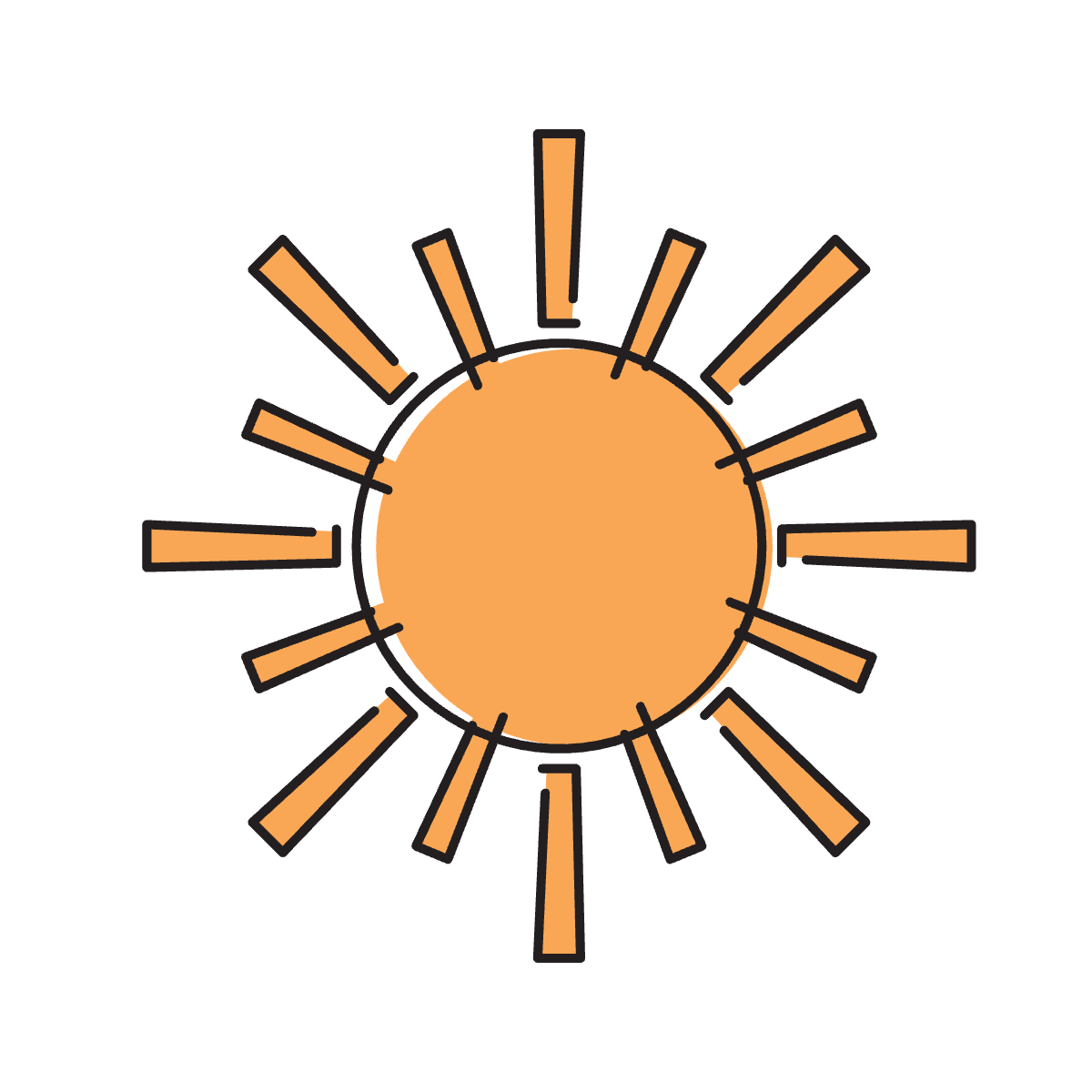
記事へのコメント